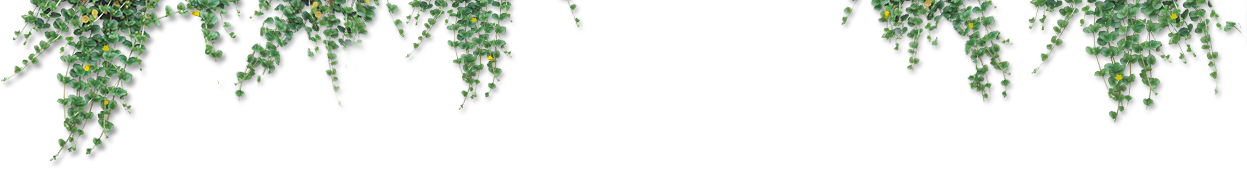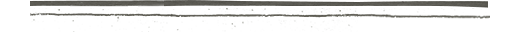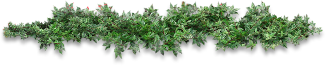
東文彦と三島由紀夫のこと
第4回東文彦研究会を終えて
先日、予定通り第4回東文彦研究会を無事に終えることができました。
活発な議論がなされ、参加者の皆さんにはお礼を申し上げます。
「岬にての物語」にはダヌンツィオ『死の勝利』の影響がないことを実感していただけたと思います。
また、ダヌンツィオとは全く異なる三島の表現のすばらしさも実感していただけたようで、喜んでいます。
昨年、谷川渥さんの『三島由紀夫 薔薇のバロキシズム』で、また久しぶりに三島の「岬にての物語」がダヌンツィオ『死の勝利』を真似して書かれたかのような誤った説が唱えられ始めました。ちくま学芸文庫で本の帯でも大絶賛されていますが、このような勘違い本が堂々と出されることには怒りさえ感じます。
早く正しい認識が広まってほしいものです。
また、同時に、正しい説を広める努力を私もすべきだったと反省しています。正しい論文を書けば、ほっておいても自然と正しい認識が広まるものだと安易に考えていましたが、現実はそうではないですね。
偉い小説家が言っているから、何人もの専門家が言っているからというだけで、しっかり確かめもせずに、誤ったことを自信満々にどんどん吹聴する評論家や出版社がいることに驚きました。
しっかりと三島の作品を読む人は、今の時代には、減ってしまったのではないでしょうか。
三島の表現のすばらしさを、できるだけ多くの方々に知っていただくために活動するということは、私の大事な使命であることを実感しました。早く三島についての誤解が解けるといいな、と思っています。
皆さん、もっと三島の作品をよく読みましょうよね!
小説「中世」第1回に感じたこと
三島がもうすぐ招集されて戦地に行かなくてはならない、という切羽詰まった状況で書いた小説です。
ですから、小説全体に緊迫した感じがあります。
第一回の現代語訳をまとめてみて、感じたことがあります。
日本の中世を舞台にして、足利将軍である義政と義尚の親子を描いています。
室町時代の戦乱の状況が、第二次世界大戦最中の三島の当時の社会状況にぴったり合っていますね。
もうすぐ戦地に赴こうとしている義尚の言葉に、死を覚悟しているのだけれど、親しい人には大丈夫だから、戻ってくるから、という感じで会話しているところなど、当時の三島の心境と同じだったのだろうな、と感じます。
また、能を上演中に鼓を破ってしまった演奏者に対して、義政が非常に怒って御手討ちにしてしまう、つまり直接斬り殺してしまう場面は、軍国主義の昭和初期にあって、暴力的に𠮟りつけるような兵士や上官を連想しました。
「中世」とは、戦時中の生活のいろいろな要素が色濃く投影されて書かれているのだな、と実感しました。
「中世」現代語訳1
10代の頃の三島を知るために、小説「中世」を読んでみようと思います。
三島が19歳の頃に書いた小説です。
とても難しい文章や言葉で書かれているため、なかなか読みにくいです。
そこで、かなりくだけた現代語に訳してみたいと考えています。
第一回~第七回までと、さらに大団円に分かれているので、一つずつ現代語にしてみます。
疑問やご意見がありましたら、お寄せください。
今回は、第一回の現代語訳を添付します。
![]() 「中世」現代語訳1.pdf (0.18MB)
「中世」現代語訳1.pdf (0.18MB)
白い花
文彦というと、どうも白い花が連想されるようです。
文彦に小説の指導をしてくれていた恩師、室生犀星は、文彦が亡くなった約1年後に追悼文を書いています。
その最後には、文彦に捧げられた追悼の俳句、つまり「悼句」が付されています。
「白菊や誰がくちびるになぞらへし」というものです。
文彦は小説で魅力的な少女を書くのが得意でしたが、その少女達は、誰がモデルなんだろうか、というような意味だと思われます。
白菊のふっくらした感じと、少女達の唇の感じが似ています。
また、白菊の清らかなイメージは、文彦という人物の清らかな感じに通じています。
そして、やはり亡くなってしまった文彦に捧げられた白菊が連想されます。
さすが犀星だな、と思われる俳句ですね。
犀星は生きている文彦に会ったことはなく、亡くなった顔を初めて見て、美しい青年だと思ったと、追悼文に書かれてあります。
友人、三島由紀夫もまた、文彦を白い花になぞらえています。
文彦が亡くなった当時18歳だった三島は、文彦の葬儀で、友人代表として弔辞を読みます。
その読み上げられた言葉の中で、文彦を白梅にたとえます。
文彦の清らかさについて、「雪の内なる白梅のおもかげもありけるものを」と述べているのです。
親しい人達の多くが、文彦を白い花に結びつけていることからは、文彦の個性が感じられます。
東文彦の本名
東文彦の本名は、とても珍しい漢字です。
東徤(あずま・たかし)です。
「徤」は、〈ぎょうにんべん〉に「建築」の「建」です。
この文字は、中国の古代思想、『易経』の注釈書の中に出てくる文字で、世界中でその一箇所だけで、おそらく使われている文字です。
易経は、占いの易の元になる思想です。
易経では、天が充実して活動している状態を理想としていて、それを「徤(けん)」と呼びます。
人間や、その他の生き物、または事物や自然現象が充実している状態のことは、「乾坤」の「乾(けん)」という字を用いて呼びます。
文彦のおじいさんである東武(あずま・たけし)さんが、かわいい孫に易経の理想を表す文字を、名前につけてくれたのです。
中国思想や中国文学について、詳しい知識を持ったおじいさんでした。
この名前によって、文彦は小さい頃には苦労もあったようです。
文彦の小説には、易経の世界観を表現したものがあります。
自分の名前から着想した可能性があると思われます。
文彦と三島とは、互いに名前のことを手紙で書き送ったことはわかっていますが、詳しく書いた手紙そのものは、今のところ、見つかっていません。